
いまでは世界180の国や地域で親しまれている理想科学の製品。熱帯から極地までのさまざまな気候に加えて、顧客の業種も多岐にわたり、使用環境は千差万別です。1960年頃、海外からの引き合いも増えてきた「RISOインク」。開発者にとって、さまざまな環境下で安定した品質を保ち、きちんと性能を発揮することが、最大のテーマでした。
「RISOインク」は、油と水とカーボンが均一に混ざり合ったエマルジョンインク。1954年に理想科学の前身、理想印刷社が日本で初めて開発しました。「RISOインク」にとって、温度の変化や振動によって水と油が分離せず、品質を維持することが世界に通用するインクとなるかどうかの分かれ目だったのです。
インクに旅をさせるという発想
おりしも国際間の貿易がかつてない活況を示し始めた時代。そこで考えた創業者羽山昇(当時社長)は、知人に頼みこんで、世界の海を航行する輸送船の船倉に「RISOインク」を載せてもらうことにしました。「いじわるテスト」と名づけたインクの旅。太平洋からインド洋、地中海からシベリアまでめぐる船旅は、当然赤道直下も北極海の冷気もくぐりぬけなければなりません。とりわけ密閉された船倉の温度変化は想像を絶するほど。航海中の振動も大敵です。はたして「RISOインク」は、世界の気候という荒波を乗り越えられるのだろうか……。
「使う側のプロ」がつくる品質
1961年、2年の長旅を終えて横浜港に到着したインク。おそるおそる開けてみると……みごと期待に応え、正常な状態を保っていました。その後もお客様が世界中に広がる中で、あらゆる環境に対応すべく実験を重ね、品質向上そして新製品開発につなげていきます。
もともとは謄写印刷業からスタートした、理想科学。それゆえ、私たちはもっとも厳しい目でインクを選んできました。お客様に満足していただける最高品質のインクを提供する。それは、単なる「つくり手」ではなく、「使う側のプロ」でもあるからこその責任であり、矜持でもあるのです。

さまざまな環境を想定し評価を徹底
写真の環境試験室では、一般的なオフィス環境(15℃〜30℃)を超えた、さまざまな使用環境を想定。紙質の異なる用紙、インク使用量の異なる原稿を使用、サプライ(消耗品)、ハード(機械)ともに、どんな条件下でも問題なく印刷ができるかどうか、つねに確認を重ねている。

使いやすさも追求
ユニバーサルデザインの採用や、やりたいことが直感的にできるユーザーインタフェースの実現など、お客様の潜在的なニーズに応える製品開発に積極的に取り組んでいる。

厳しい評価の繰り返しが
クオリティの高い製品づくりを可能にする
多枚数プリントを処理する耐刷力、操作性のよさ、高品質な印刷を可能にする消耗品の提供…。これらを可能にしているのが、理想科学がこだわる、徹底した品質評価です。
インクなどの消耗品は、さまざまな保存状況下でも変化しないものを。プリンターは、温度や湿度などの異なる環境、異なる紙の種類でもスムーズに稼働するものを。両者がきちんとマッチングし、さまざまな環境において問題なく印刷できるかを実験して、問題があればすぐに各担当部署にフィードバック、そして再調整。開発段階から繰り返される厳しい評価が、クオリティの高い製品づくりを可能にしています。
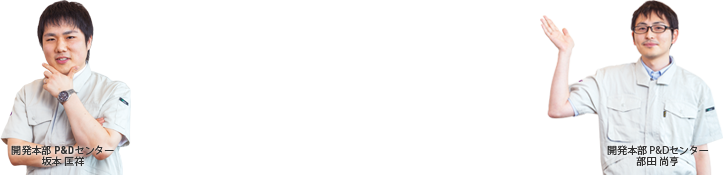
別の号の「世界に類のないものがたり」
